中学受験って正直、僕はあまりピンと来てないんですよ。自分自身が経験してないし、小中の頃は計算だけは早かったけど全体的には真ん中くらい。地元の中学から高校に行った普通のタイプです。
でも、完全中高一貫の進学校で講師をしてたことがあって、そこで感じたのは「ここはすごいな」ってこと。先生たちは院卒ばっかりで、大学数学レベルを知っていて当たり前。生徒も中学受験を勝ち抜いてきた猛者ばっかり。純粋な数学力だけで勝負したら、僕なんか天狗になってたけど通用しない世界でした。僕の教員としての特技は「できない子へのアプローチや対応力では負けない」と思っていますが、贅沢な環境やなあと思えるぐらいにすごい人が多かったです。
そして生徒の地頭の良さも本当にすごい。学力的にも体力的にも厳しい中学受験を乗り越えてきた子どもたちですから。僕が「う◯こー」とかはしゃいでいた時期でも、知識を素早く吸収してきた子どもたちは違います。でも同時に思ったのが「こういう子たち、公立中からでもトップ取れるんじゃないか?」ってこと。他塾ですが神奈川で高校受験と言えばSTEP
あそこのノウハウは正直段違いだと思っています。
そして、そこに通えば普通にトップ校に行けるくらいのポテンシャルは十分にあると思います。
だから僕は、中学受験って本人の意志と、最悪無駄になってもいいやって親が思える余裕があればやればいい。でも本人がそこまで乗り気じゃないなら無理にやる必要はない。
一つ目は、いい中高一貫に進学したからといって必ずしも成績が伸びるとは限らない、という点です。
中学受験を突破する子どもたちの多くは、純粋な好奇心で勉強しているわけではありません。なぜなら、中学受験の勉強は知識偏重で、必ずしも面白い内容ではないからです。それでも必死に取り組むのは「褒められるから」「他の子に勝てるから」「達成感を味わえるから」といった理由が大半です。
しかし入学すれば、同じように優秀な子どもたちが一堂に会します。その中で再びトップを取るのは難しい。トップを取ることを唯一のモチベーションにしてきた子が、挫折に直面したとき、好奇心というスパイスを持たない限り、勉強に向かうこと自体が嫌になってしまう。これが、いわゆる燃え尽き症候群です。
さらに二つ目は、中学受験で学んだ知識が大学受験ではほとんど活かされない、という点です。
特に数学では顕著です。中一・中二の段階で「◯◯算」や「特別な公式」を多用するクセが残っていると、数学が「論理の学問」であるということを一から伝え直さなければなりません。中学受験の算数は、知識やパターンを頼りにクイズのように解く側面が強く、本質的な数学とは異なるのです。もちろん圧倒的な演習量で公式を身体に染み込ませる訓練には価値がありますが、それは「答えを出せる」力であり、「論理的に考える」力とは別物です。
実際、中学受験の算数には、元数学教員の僕ですら初めて知ったような公式がいくつも出てきます。これは、大手塾が小学生でも難問に対処できるように生み出したノウハウです。「◯◯算」と呼ばれるようなテクニックは、中学受験の舞台だからこそ成り立つ特有のものです。
ただし限界はすぐ訪れます。例えば中一の一学期に学ぶ方程式の文章題。単純な問題であれば中学受験で鍛えた割合の公式を駆使して答えを出せるかもしれません(多くの先生はバツをつけるでしょうが)。しかし方程式はすぐに複雑になり、その場しのぎのやり方では対応できなくなる。実際、進学校の生徒でも「等式の意味」を理解できていないケースは珍しくありません。一方で、公立中で平凡な成績だった生徒の方が、等式の本質をきちんと理解していることもあります。
中学受験で培った力に全く価値がないとは言いません。しかし、それだけでは太刀打ちできないのが数学です。高校に上がる頃には、中学受験で得たもののうち実際に残るのはせいぜい「四則計算の速さ」程度、ということも珍しくないと思っています。
だからこそ、僕は小学生にとって大事なのは「基礎計算」と「比・割合」への理解だと思っています。中学受験の合否に縛られなければ、そこにじっくり時間をかけられる。例えば小学校の文章題を通じて「等式の意味」を深く扱い、早めに方程式を導入して移項から正負の数を扱うことだって可能です。
もちろん難関中合格を目指すなら、回り道をせずに大手塾のテクニックを徹底的に学ぶのが最適解でしょう。それは悔しいですが、事実です。
ただ「数学のための算数」を学ぶのであれば、もっと多様な方法があるはずです。
関数の意味とは何か。確率でなぜその式が成り立つのか。そうした本質的な理解を身につけた人が「数学というゲーム」において最終的に勝者になるのです。
で、もうひとつ強く言いたいのが英語です。
進学校の子たちは英語が本当に強い。中学で準1級とか取る子もいるくらい。英語は算数や数学と違って、演習量と語彙シャワーでどんどん伸びるんですよ。だから中学受験しない子は、英検を一つの目標にするといい。英語については、もっとはっきりと「致命的な差」があります。
公立中学校では「卒業までに英検3級が取れれば十分」とされます。よほど賢い子が独自に頑張っても、準2級までが関の山です。
しかし私立の進学校では違います。中学受験を突破してきた子どもたちは、すでに「学ぶ体力」と「吸収力」が担保されている。だから英語の語彙力もどんどん積み上がっていきます。実際に、僕が勤めていた中高一貫校では、中学生で準1級を取得する生徒も珍しくありませんでした。
さらに修学旅行が海外だったり、交換留学や海外研修などの機会も充実していて、文化や言語を肌で体感するチャンスも多い。こうした経験の積み重ねが、公立との大きな差を生みます。
だからこそ、公立中に進むなら「どう置いていかれないか」が大きな課題になります。
せめて小5くらいからは、2年先ぐらいの内容を先取りして学ぶくらいで、ようやくスタートラインに立てるのではないでしょうか。
幸い、中学受験組はほとんど英語に触れていません。主戦場は国・算・理・社の4科目だからです。つまり、中学受験をしないからこそ「英語に先に手を付けられる」強みがある。
僕の感覚だと、数学は「攻めの武器」で、英語は「守りの防具」。数学が強ければ一気に突き抜けられるけど、英語で遅れると受験全体で致命的になる。だから「算数で基礎固め+英検で差をつけない」っていうのが、公立中からでも進学校と渡り合える戦略だと思います。
というコンセプトの小学生の塾作ろうかなー
数学を視野に入れた算数と、中一で英検三級を目標にした塾
かつ良心的な価格。
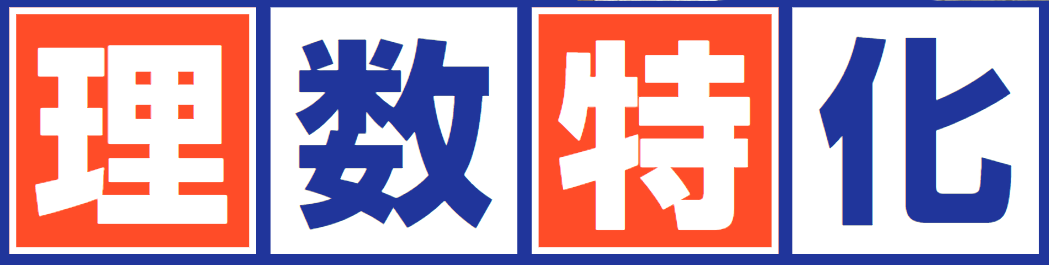

 Contact
Contact