イライライライラ
僕自身、いま1人暮らしをしていて、3食ともに自炊という日が多いです。さらに惣菜や弁当なども基本買いません。とはいえそこまで手の込んだものを作らないのでだいたい肉か魚と玉子を焼いて食べるぐらいです。料理好きというわけではありませんが、摂るべく栄養素を調整できるので大体自分で作ります。たまに知り合いとする外食では好きに食べます。
そして料理してイライラすることがあります。たまに変化が欲しくて、こんな料理を作ろうかなとレシピを調べると
塩 適量
もうこの表現を見ると、レシピのページを閉じたくなります。
適量ってなんね。きっとレシピを書いた人は数学できないなって心の中で批判しています。
料理できるんだねと言われることはよくありますが、そんなことはありません。でも美味しい料理を作ることってそこまで難しくなく、レシピ通りにやればそれなりに美味しくなると思っています。料理が下手って人はだいたいレシピにはない変なオリジナルを加えようとするか、火加減や塩加減をこなせないかのどちらかだと思います。あとはどうにかなります。だから初めて作る料理で塩加減が適量なんて言われても、僕はぜんぜん分からないわけです。せいぜい気持ち少なめにして、後から足すぐらいしか。辛すぎて台無しになってしまった日には涙も止まりません。
僕は曖昧な表現というのが好きじゃありません。学校現場では特に曖昧な表現がかなり好まれているように感じます。
なるべく早めに出してください→納期を具体的に言え!
できるだけ配慮して→配慮って何!事例をいえ!
前と同じ感じに→前って何!?
臨機応変に→判断基準ゼロで判断とかもはや心理テスト
曖昧な指示って責任の所在を、個人の主観に依存してしまうから嫌なんですよ。なるべく早くと言われたものに対して、僕にとってのなるべく早くは半年ぐらいを目処と思っていました、なんて言われたら反論できますかね。「普通に考えればわかるだろ」としか言えないと思います。僕は適度に加減するということが苦手なので、具体的じゃない曖昧な表現を聞くだけで集中が削がれます。僕は仕事仲間がいる環境は好きなのですが、人と一緒に仕事をするのは好きじゃないです。今の塾は業務委託している人は若干いますが、誰も雇用せず自分が見れる範囲で見ているのにはそういう理由もあります。
数学では1+1=2.0000001なんて書いたら当然×ですが、社会ではこれを認めない人には「ほぼ2
じゃん」と突っ込まれ、きっと異端児です。じゃあ2.01なら?2.1なら?2.4なら?と考えても認める人と認めない人の割合が変わるだけでキリがありません。
なぜ数字で伝えることが大事なのか。数字で言えれば人の感覚に依存しないからです。
塩適量って言われても料理に慣れてない人からすると、その人なりの感覚によって適量が入れすぎてしまう可能性だってあるわけです。さらに言えば数字での指示であれば、検証と評価ができるわけです。例えば塩が大さじ1杯(約15g)となって、例えばそのレシピを書いた人が塩加減濃いのが好みで自分に取って辛かったとすれば、じゃあ次は12gとすることだってできるわけです。「いやそんなん感覚で少なくすれば」って人もいるかもしれませんが、そういう人はそもそも料理に慣れている人で使う材料さえ知っていれば自分で味を整えられる人です。僕みたいな素人には無理です。
「数字で考えることが嫌い」という人が増えていくと僕みたいなポンコツにとっては生きにくい社会になってしまうわけです。なので、数学だけは頑張ってほしい。
英語の授業の目的は英語でコミュニケーションを取れるようになるため
社会の授業の目的は社会の知識を身につけるため
数学だけは違います。言い切りますが、数学の知識なんてほとんど役に立ちません。知識で言えば英語と情報が最強だと思っています。三角関数?微積分?もちろん社会に取っては必要になりますが、個人が生きていく上で使うことはほぼありません。
でも数字で考えるのが苦手という人は、数学を勉強することを避けてきた人だと思っています。数字で考えることがくせがある人は話していてわかります→(ああ、この人きっと数学は得意そうだなって)
フルスマに入ると段々と思考が理系っぽくなってくるような気がします。特に一年以上いる生徒には、よく思います。この前なんて生徒に宿題を自分で自分が必要だと思った部分をやっておいでと言ったら「具体的に指定してください💢」って言われましたからね。、、とても嬉しく感じました。
まとめ
お願いだからレシピは“g”で書いてくれ。
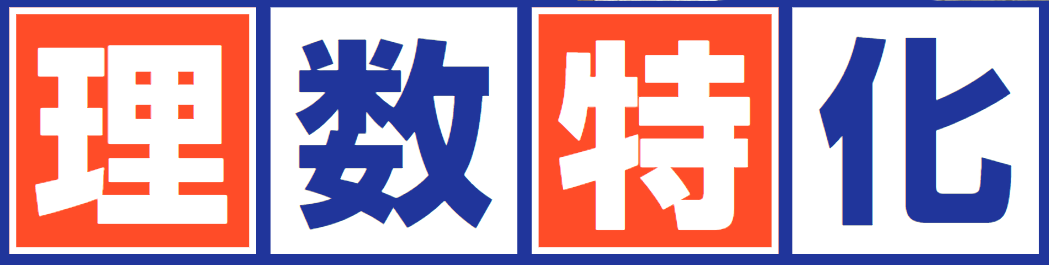

 Contact
Contact