この記事を読んでいるあなたは僕(カトウユウタ)に会ったことありますか?
僕に会ったことがある人でしたら厳しい先生か甘い先生かでいえば、きっと「この人甘い先生だな」と分類されることでしょう。
同僚の先生にも「生徒に強く言うこと出来ないでしょ?」みたいに言われることも割とありました。
「強く言わないとわからない子がいる」「ビシッと言わないと」学校現場ではよくある考えみたいなのですが。僕はこの考えが嫌いです。答えは脳の仕組みにあると思っています。
脳の危機対応のメカニズムには防御システムと言われるものがあります。脳の奥底にある扁桃体と言われる小さな部位。ここには人間の感情、特にネガティブ感情について重要な役割を果たしていると言われています。大きなストレス禍に置かれると人は「Fight or Flight」反応(戦うか、逃げるか)と呼ばれる状態になります。簡単に言えば草食動物がライオンに遭遇したときの感情です。汗がでて、思考も止まり、今すぐ行動をしないと‥というような状態です。そして重要なのはその防御システムと学習はめちゃくちゃ相性が悪いことです。この防御システムが活性化しているときには脳の前頭前野の活動が押し下げられることがわかっています。前頭前野は知性や理性など人の知的な活動を司る部位です。危機状況においては、時間をかけて物事を考えることは命取りです。だから防御システムは知性のシステムを止めて、行動を早めさせるわけです。
子どもに教えるときに大事なのは行動を変えさせることではありません。思考させることです。強く言われた子どもが取れる選択は二つだけです。FightかFlightか。でも経験上は強く言う側はある種の主導権を握っている側なので、体感9割以上はFlightの選択を取ります。ライオンであれば物理的に走ればいいわけですが、そんなことをしても余計に怒られるだけです。なので「謝る」「言うことをきく」ぐらいしかしないと思います。強く言うと何が変わるのでしょうか?確かに行動を変えさせるには効果的でしょう。でも頭が真っ白になるわけです。強く言ったところでお互いが疲れるだけです。そんな思考停止の状態にエネルギーを割いて、「あれだけ強く言ったのに」とまた強く言いすぎてしまう負のループになることが予想されます。脳の仕組みを考えると僕からすれば強く言うことは思考を停止させることに等しいわけです。
もちろんそれでも強く言わなければならないこともあります。学校の先生としては
1不法行為
2危険な行為
3人権侵害行為
はなぜかを理解していなくても、上の行為を辞めさせるために強く言う必要があるとは思いますが、逆に言えばこれぐらいですね。
僕の塾の目標は考えることを好きになってほしいことです。だから、僕が怖いから宿題をやらなかればならないという状況はアンチシナジーなわけです。誰がそんなに嫌々やることを好きになるのか?反省するにしても、「先生が怖いから次から気をつけよ」じゃなく「自分の夢を叶えるためにはこの行動は良くなかったな」と内省してほしいわけです。
話はそれましたが
叱るを多用する先生に聞きたいのは
強く言うことに教育的な価値はありますか?あなたは偉そうな人の言うことを思考停止に従う人を作りたいのか。
前提として厳しい先生は尊敬します。強い指導をするのは言う方も疲れると思います。ほっとけば一番、楽なのに見過ごさないのはある種の責任感だとは思います。でも強く言われ続けた子達が立派に未来を切り開いていける人材になれるかといえば、良く言っても従順さぐらいです。僕は大人の都合のいい仕組みに巻き込まれるような子どもには育てたくありません。自由で、他者を尊重でき、自分の好奇心にそって活き活きとした子どもは、生徒だろうが尊敬に値します。
断言しますが、多様化と情報化が進む近代で活躍できる唯一の武器は「好き」と「数学」です。
これがあれば、無双です。昔は自分の夢を叶える職なんてスポーツ選手か歌手ぐらいしかいなかったと思いますが、今はいろんな道があります。スポーツ選手がプロになりきれなくて、その努力をyoutubeで発信して、大きなスポーツ会社を作ることもできます。高校から商業高校に入り、簿記の勉強にフルベットして税理士として大活躍する道だってあります。一昔前と違い一流の素質がなくても、自分の好きに従って進める行動力と、それを形にする教養があれば大体のことはできると思います。苦手なことはchatgptのおかげで、極力カバーすることができています。僕は平成7年生まれですが、そういういまの時代が好きですね。
でもどっちが大事かと言えば「好き」です。好きにそって行動していれば経験は得られます。知能はできる人に借りればいいわけですし。自分に子どもができたら「関心を持って、干渉はしない」をモットーにしたいです。もともと人間は好奇心が備わっているから、余計なことを言わず、安心して取り組める環境があれば勝手に好きを見つけてくれると思います。「◯◯すべき」「◯◯しないべき」と変に教え込むから、破綻するわけです。もし勉強をしてほしければ、自分が勉強する姿を背中で見せて、勉強は楽しいのかと思い込ませよう。
というのは大義名分です。
実は一番大きいのは僕自身が社会人でも稀に見るぐらいポンコツで大人の前ではなんとか隠しますが、生徒相手でもボロが出ることが多いので、子どもに完璧を求めない代わりに自分のポンコツを許容してもらおうと腹づもりです。
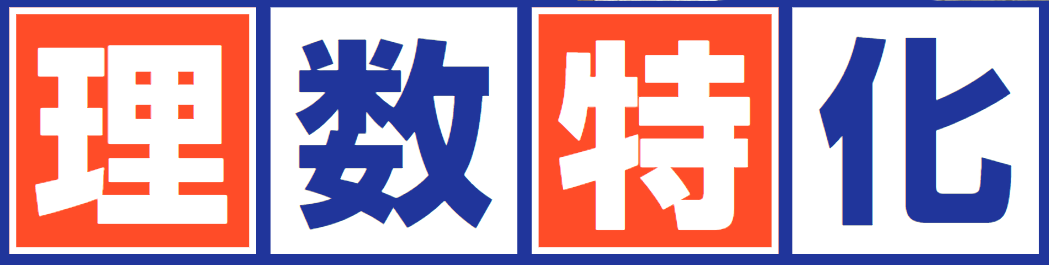

 Contact
Contact