「中3で英検3級ってだいぶ遅めの授業なんですね」
我が塾では数学理科を中心に見ていますが、試験前では英語や社会なども見たりします。何人かには英検三級の対策授業をしていたのですが、それを中高一貫校に通うオンラインの生徒に言ってみたら、言われました。知っています、そこには悪意は一切ありませんし、その生徒の中学では中学卒業で3級どころか準2級持っていないと相当遅れている環境です。そこまで超進学校というわけではありませんが、中3で3級は遅く感じるのは当たりまえですよね?
中高一貫校に通う生徒はなかなか実感がないと思うのですが、公立中出身の僕からすれば「わー」って感じです。公式的には
英検三級は中学卒業程度 という難易度設定なのです。
公立中の生徒ではそこそこの学力を持つ生徒でも2級まで持っている生徒などほぼいません。標準的なカリキュラムを受けて、公立高校の入試を目標に頑張っている生徒では割と良くても中3で準2級です。
中高一貫校に通う生徒はやはり英語が強いんですよね。前に僕がいた学校は国際系の進学校だったので当然なのですが(小学生で準1級とった生徒もゴロゴロ。最初の方の授業で僕が留学生相手に意図を伝えられなくて周りの生徒がみんな上手に翻訳していたのに驚きました。)、他の中高一貫の生徒でもやはり英語が強い生徒が多い。というよりも標準的な公立中学の進度では、難易度のインフレが激しい英語を突破することがかなり厳しいです。僕は2014年入試で10年も経ったぐらいですが読み解かなきゃならない英語の分量も相当増えました。中高一貫校ではそれがわかっているから、どんどん先取りして、大学受験で突破できる英語力を仕込むわけです。
文理選択において
国立のようにたくさんの教科をやりたくないって人は私立大学志望で英国社の文系か英数理の理系をどちらか選びますよね?多くの人は数学が得意なら理系、苦手なら文系だと進路先を選ぶ生徒が多い印象です。英語は理系文系どちらに進もうが避けることが難しいですが、特に私立文系では英語力が9割だと思っています。
難関大の入試で国語や社会ではあまり差がつきにくい科目です。難関大特有の記述試験に原因があり、文中の表現や知識を使って部分点を集めることこそ難しくはありませんが、満点答案をすらすらと作ることは受験の最前線で研究している熟練の予備校講師ではないと難しい。となれば、大きな差を作ることになるのは英語です。英語はだいぶ差がつきます。さらに配点も英語に傾斜がついていることも多いです。なんなら一般入試の前に英語を活かして、パスしてしまう生徒もいます。それが分かっているからこそ、誤解を恐れずに言えば上流な家庭ほど子どもを海外の文化に触れさせることが多いのです。英語が実用的な面でずば抜けて得意というのは受験に置いても将来に置いても、大きな有利になるでしょう。
理系はどうでしょうか。数学も理科は本人の努力に大きく依存し、点数の差もかなりつきやすいです。数学や理科は努力次第では満点を目指すのも努力によっては難しくないと思っています。難関大の入試でも理系科目で高得点獲得している生徒はそこまで珍しい存在ではありません。ちなみに僕は東工大(現在の東京科学大学)落ち早慶理工受かりですが、東工大の得点開示で数学が273/300で英語が9/150というなんとも極端な数字でした。「数学は才能」とよく思われがちですが、僕は1番誰でも出来るようになる科目だと思っています。むしろ読解力や記述力など幼少期からの素養が問われやすい文系科目のほうが逆転可能性が低いと思います。理系なら英語が多少苦手でも数学や理科でしっかりと取り切ってしまえば合格できます。なんで数学は才能なんて勘違いされやすいか。
「えぇ、授業の内容全然理解できない…でも隣のAくんはすらっと理解してどんどん進んでいる、私は才能がないに違いない」
こんな感じの生徒を学校で大量に見てきました。でも本当に理解できていない原因は才能ではなく過去の蓄積の欠如です。関数とはそもそも何か?ということが分かっていない人がどうして微積分を理解できるのかという話なのです。問題を解けることと、根本の土台を理解していることは全く異なります。手っ取り早く偏差値を5上げたいのであれば問題を解くことに重点を当てることも有効かもしれませんが、長い目でみれば必ず躓きます。
英語だけなく数学も中高一貫校は一年早く授業が進みますが、英語ほどは大きなアドバンテージにはならないと思っています。塾業界では先取り学習こそが偏差値UPの近道だ!という意見が多いように見えますが、僕は反対です。早く進めて、高校三年生で受験対策に回せるというアドバンテージがあるのは分かります。でもその程度です。そのスピードの代償に大事なものを失っていれば逆効果です。僕は公立中→公立高で、地元では進学校の部類でしたが高3の範囲が終わるのも3年夏休み過ぎです(さすがにちょっと遅い)。
僕の塾のオンラインの生徒のほとんどが中高一貫校で数学は一年早く進んでいます。彼らに何をしているかと言えば、学校より先に進めることはしません。学校は十分早いんだから、それ以上に進める必要はありません。それよりは基礎の内容を深掘ります。
教科書に書いてあるような土台がキッチリとあれば、高2までは全統65は行くものだと思っています。先取りして問題集しっかりとやっているのに偏差値が50ぐらいしかないというのは何かしらの基礎の抜けがあるはずです。「sinってそもそも何?」「組み合わせは何でCで計算できるの?」「二項定理はなんで成り立つの?」そういった話をひたすら僕が聞いていきます。すらすらと言語化できる生徒はだいたい偏差値70を超えています。それが数学力の差です。英語でいえばmath gapです。その状態になれば未習分野だって教科書見ればやりたいことは分かるし、模試で難しい問題の解答を見ても理解が早いです。でもこれは先天的なものではありませんと断言します。僕はその土台を作る建設業のような仕事だと思っています。
僕も定期テストを何とか突破したく、大学受験もそこまでは考えていないという生徒にはそこまでは求めていません。出来るだけ労力をかけずに、定期テストで高得点を取れるような授業をしています。でも難関大を目指す人にとって、基礎の抜けはあまりにも致命的になるので、先取りよりも結果的に基礎の確認作業に手を回すことが多くなっています。
凡人こそ理系行け。
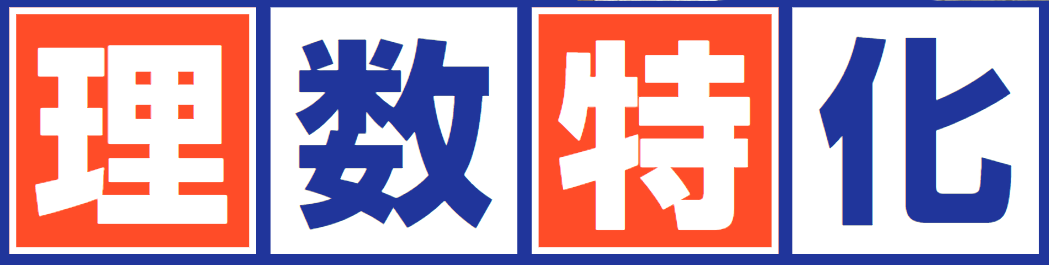

 Contact
Contact