こんにちは。最近は高校生の生徒も徐々に増えてきて、大学受験の進路について話しをする機会が増えてきて、高校生三年生の担任をしていた時代を思い出してきます。
僕が初めて学校教員の担任を持ったクラスは専門志望と大学志望が半々ぐらいのクラスでした。だから大学へ行こうか、専門へ行こうか迷っている生徒がたくさんいました。僕は学校の先生として「お前こっちのほうが向いている!こっち行きなさい!」という感じに引っ張るような強い進路指導するタイプが好きでありません。「大学と専門はどんな違いがあると思うー?」「どんな仕事をしていたらハッピーだと思うー?」みたいなサッカーのディフェンスのようなスタイルでした。幸いにも僕のクラスは「〇〇をしたい!」と明確な意思を持つ生徒が多かったのでそこまで気に留めることもありませんでしたが、高卒の進路で迷う生徒は多いと思います。「とりあえず大学へ」という風潮には反対です。
例えば大学行って、「微生物」について研究したい!という生徒であれば迷うことなく大学へ行くと思います。自分の好奇心に答えられる環境としては大学は素晴らしい環境だと思っています。しかし大学と専門で迷うような生徒のほとんどは、好奇心に従って本当に勉強したい気持ちありますか…?って感じの子が多いです。これは構造的な問題として、そもそも日本の高校生でどれだけ興味に応じた進学をしているのやら。「これを勉強したい→大学へ行こう」ではなく「大学へ行こう→この中ではこの学部かな」という動機付けでしょう。
大学と専門学校のざっくりとした違いは何でしょうか?僕からすれば大学は「役に立たないこと」を学ぶ場所。専門学校は「役に立つこと」を学ぶ場所です。大学の学部をイメージしてみてください。経済学部、理工学部、商学部、法学部、文学部、総合政策学部…。あなたの将来に明確に役立つものはありますか?学問は役に立つかどうかの基に存在しているわけではありません。仕事と大学で学んだ内容が直接リンクしている人は多くはないでしょう。あくまで教養を学ぶ場に過ぎないわけです。一方で専門学校は役に立たないことなど一切学びません。即戦力になる人材を二年間で育て上げるには、そんな暇はありません。専門学校は地雷と言われる学校が少なくないので気をつける必要はありますが、基本的に先生方は熱心です。何としても希望するような就職につけるように熱い感じです。どちらかというと高校に近いですね。美容師になりたい。システムエンジニアになりたい。動画編集者になりたい。調理師になりたい。保育士になりたい。ほとんどが職業があってのカリキュラムです。学問よりもとりあえず食べるのに苦労したくないという人にはいい場所じゃないですかね。
大学とは趣味の世界です。医者や薬剤師、教員など大卒でなければ取れないような特定の仕事を除けば、行った方いい理由は一切ありません。学びたいことがある人が行きたくなるような場所だと思っています。ひと昔まえでは大学へ進学希望する高校生が少なく、大学卒業したということ自体がある程度のステータスになっていた時代もありました。しかし今は大学進学する生徒のほうが多い時代です。これだけ少子化が進んでも、大学はほとんど潰れません。とりあえず大学行けば手に職がというのはフィクションの世界です。
もう一つあまり取られないのは就職という選択肢です。
専門学校へ半分ぐらい進むような学校でも就職する生徒は自分のクラスではプロのアスリートを除けば、1人だけでした。リスキーな選択と思われ、懸念されがちだと思います。気持ちは大いに分かります。でも例えば僕が今の記憶のまま高校生にタイムスリップしたとすれば、きっと大学進学は選びません。同じように塾を経営していくというのはズルなので専門知識は引き継がないとすれば、色んなところで働いてこれだという道で自分で事業していく道を選ぶでしょう。就職は最も合理的な選択だと思います。
日本の学生はバイトの給料が安くて文句も出ると思います。でも経営者からすれば、最低時給の存在で新入りにも払わなければならないので、バリバリ活躍している人の給料を上げるのは構造的に難しいのです。普通に考えれば教えてもらう身分の新入りに1162円払っているのに、そういう人たちに教えながら誰よりも現場を回している優秀な人には良くても1500円ぐらいしかもらえないのは理不尽ですよね。逆に新入りはお金をある程度貰いながらスキリングが出来るという最高に恵まれた立場です。経営者になれば学ぶためにはコンサル会社などに相当なお金を払わなければならないですからね、羨ましい限りです。1つの環境に長くいる必要はありません。本当に大事なことは半年もいないうちに身についてしまいます。将来、その道に進むとなれば、みんながスタートする前にスタートしているという合法的なフライング状態あり就職のときなどにも現場経験というものが活きてきますし、本当に強いのはその道を進まなかった場合です。塾を経営したことがある人が税理士になれば、塾を経営したことのある税理士になることが出来ますからね。意味わかりますか?シナジー効果です。打てるし、投げれる大谷翔平のような存在です。
色んな道にどっぷりと浸かることが出来るのは10代の特権です。僕は大学卒業するまでに塾ぐらいしかバイトをしたことがないことをやや後悔しています。もっといろんなことをすれば良かった。なので正規教員を辞めて塾を作って生徒があまりいなかった時代には色んなバイトをしています。半年でスイミングスクールのコーチ、スポーツジム、模試の採点、スケートリンクの設営、ポケモングッズの販売、夏祭りのスタッフなどなど色んな仕事をしました。悪い言い方をすればノウハウをお金を貰いながら、奪ってやったわけです。唯一、就職を選んだ僕のクラスの生徒は自由で自立心のある賢い生徒でした。学校の勉強などそっちのけでバイトばかりやっていましたが本当にたくましい生徒でした。今頃何やっているんだろうか。高卒であえて就職の道を選ぶには自信は必要で高校生活での経験値が鍵だと思います。みんなが四年かけて、役に立たないことを学んでいる間にも10代後半20代前半という脳が冴えている時期に経験を積めるわけですから、非常に合理的です。
僕はコンビニやマックなどのようなバイトは初バイトなどではいいと思いますが、ずっとやっているのはあまり良い選択ではないと思います。web制作、経理、塾講師などスキルが上達すれば、活きていくものを自分の興味に応じて選べれば理想的だとは思います。その道を選ばなくても、シナジー効果で大谷翔平になれる可能性がありますからね。バイト禁止の高校なんてbakaだなあと思っています。どうせ影でやっても把握できないでしょうに。どうせやるなら堂々と応援すればいいのにね。
もう一つ
一年前の話ですが。
あるフルスマ生の話。その生徒は自分が勤めていた学校の元生徒で学校で数学の授業を見ていた関係にありましたが、大学進学後にフルスマに入りました。その生徒が言うには「そこまでレベルの高い大学ではないところに進学して、いま学校で学んでいるものが役に立たない気がして、ここから四年間役に立たないものを学び続けるのは苦痛でしかない。名前の売れたもっとレベルの高い大学へ入りなおして変わりたい!」として大学を辞めて自腹で塾代を払い、我が塾に入りました。勉強もしながら進路の話をよくしました。大学進学は自分が学校を辞めた後の話でしたが、そもそも大学に進んだのが意外で、学問を学びたいというよりも早く社会で一人前に稼げるために、役に立つ技術を身に着けたいという我が道を行くタイプなので専門行ったのかなとか思っていました。
でも役に立たないことを学んでいるという悩みは少しいい大学へ進んだら解消されるのでしょうか。多分、大差はありません。大学とはそもそも役に立たないことを学ぶ場所ですから。何浪かして、そこから四年かけて卒業したら何歳になるのか。早く社会人になりたいという希望と反していないか。勉強を続けるうちにも、その違和感はどんどん強く感じていたので、授業はオンラインでやっていましたが、車で往復四時間かけて運転してそのことを話しに行きました。そしたらびっくりするぐらいあっさりと専門学校に進むと決めて、今はとても楽しく勉強をしているということで良かった良かったという話です。芯が強いタイプでモチベーションもあったので授業も楽しくやっていたので、本音を言えば塾生としては続けてほしい気持ちもありました。塾という職業はある意味コンサルティングです。志望校に行きたいという生徒に志望校に行くなと話すのは自分の中ではNGで葛藤もありました(お金も儲かりますし)。ゆっくりと一つ一つ解決していけば徐々に成績も上がって志望校に受かるよって話すこともできました。様々な要因もありましたが、しかしやっぱり学校教員時代からの付き合いだったので本当にいい選択を取って欲しかったです。僕が退塾を勧めたのは多分、最初で最後でしょう。
長くなりましたが
迷ったら周りの評価ではなく、自分を何をしたいか優先すべき。
新しい道か慣れた道だったら新しい道をいくべき。
と思います。
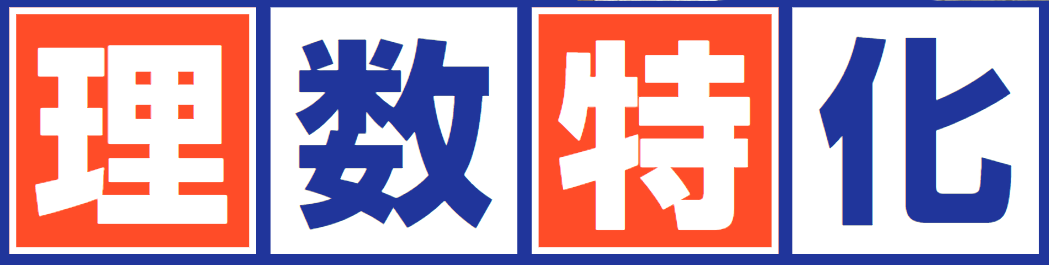

 Contact
Contact